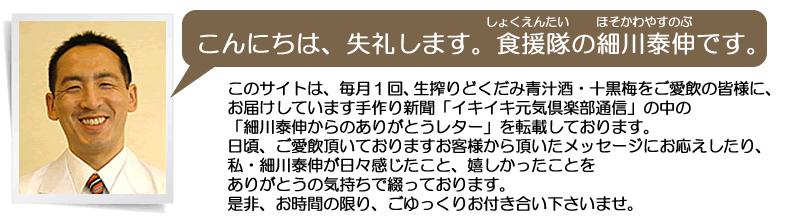こんにちは、失礼します。
生搾りどくだみ青汁酒・十黒梅(じゅっこくばい)の食援隊の細川泰伸です。
いつもいつも十黒梅(じゅっこくばい)をご愛飲頂きまして
本当にありがとうございます。
いよいよ、いよいよシーズンがやって参りました。
そうです!どくだみのシーズン、どくだみの収穫期がやって参りました。
農家さんはこの日のため、
一年通して、どくだみ畑のお世話に汗を流して流して流して・・・
今までの多大なご苦労が実を結び、感無量のことでしょう。
農家さんに、
私:「これで、お客様にお役に立てるどくだみ酒が作れます。」と
感謝の気持ちを伝えると
農家さん:「それは良かった、それは良かった」と
一段と輝いた笑顔で答えてくれました。
短い返事の中に、充実感、達成感、幸福感、
言葉では表せない大きなものを感じました。
今年は一部の畑では、霜の影響で、成長が心配されましたが、
さすが、やっぱり、どくだみです!頼もしいのなんの、
霜でやられたすぐ後から、どんどんと新しい芽がでて
しっかりと成長しております。
青空の下、このどくだみ畑に立つと、心地よい風がどくだみの葉を揺らし
とてもさわやかな空気に包まれ、心安らぐ気持ちでいっぱいです。
皆様のご想像では、どくだみ畑は、あの嫌な臭いで、
とてもいられるものではないとお思いでしょうが
全くそんなことはありません。生えているそのままの状態では、
そんな嫌な臭気はしません。むしろさわやかさえ感じます。
そして、腰を下ろし、よおく見ると、
ところどころ、今にも花が咲き始めそうな蕾が出ているのです。
明るさ、嬉しさ、晴れ晴れしさ、
思い起こせば、この畑に、どくだみを植えたのは3年前、
もともとは、耕作放棄地で、どうにもならなかった畑が、
こうして皆様のお役にたてる畑になったかと思うと、
感慨深いものがあり、農家さんのご苦労に感謝の気持ちでいっぱいです。
一生懸命、正直、真心込めて、しっかり手を掛けてやると
農作物は、ちゃんとしっかり育つし、
どこか手を抜いたり、ごまかしたりすると、
それなりの出来になってしまう。
当たり前と言えば、当たり前の事だと思うのですが、
このしっかり育ったどくだみ畑に包まれて、
何か原点のような、源のような志のようなものを感じました。
さて、話は変わりまして
定期購入で十黒梅(じゅっこくばい)をご愛飲の皆様
もうお気づきの方もいらっしゃると思いますが、
先月より、商品と一緒にお届けしています「納品書」の中に
次回のお届け予定日を明記するようにしております。
これは、お客様から
「私の次回の配達日はいつですか?」
「次の到着日が前もって教えて頂けると便利なんですが」etc
というお声を頂いておりました。
確かに、おっしゃる通り、
次回のお届け日が分からないと、受取りの準備や、
お手元の本数と日数との量の計算等々、
ご不便をお掛けいたしまして、本当に申し訳ございませんでした。
先月より、改善をしておりますので、
どうか、そちらをご確認頂きまして、ご愛飲下さいませ。
このように、弊社ではお客様のお声から改善できたサービスが多々あります。
例えば、「きょうもいちにちありがとう、おちょこ」
こちらは、最初は約30mlしか入らない大きさのものでした。
これでは、一日約30mlをお飲み頂くのに、
おちょこいっぱい、あふれるかあふれないかの量
(土佐弁では、まけまけいっぱい)で、
場合によっては、2回に分けてお飲み頂くご不便をお掛けし、
約50ml入る現行のものに改善を致しました。
それから、黒色のキャップもキャップ無しでは、
こぼれてしまう(土佐弁では、まけてしまう)
たれてしまう(土佐弁では、よぼおうてしまう)
という事で、キャップをお付けするよう改善を致しました。
もし、十黒梅(じゅっこくばい)をご愛飲の中で
何かご不便等々がございましたら、お教え頂けると幸いです。
できる範囲ではありますが
ご愛飲の皆様のお声を大切に
改善すべきは、で改善をして参ります。
今後とも、何卒どうぞよろしくお願いします。
それでは、失礼します。
細川 泰伸